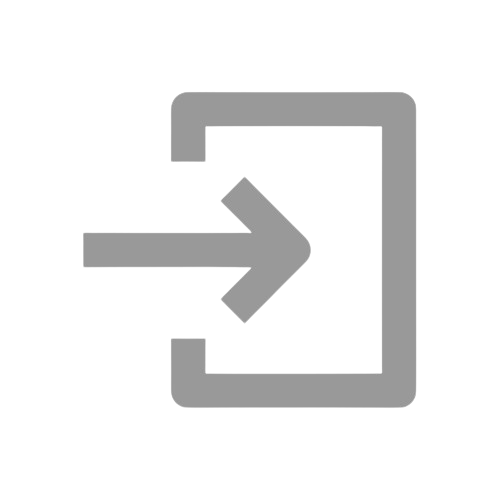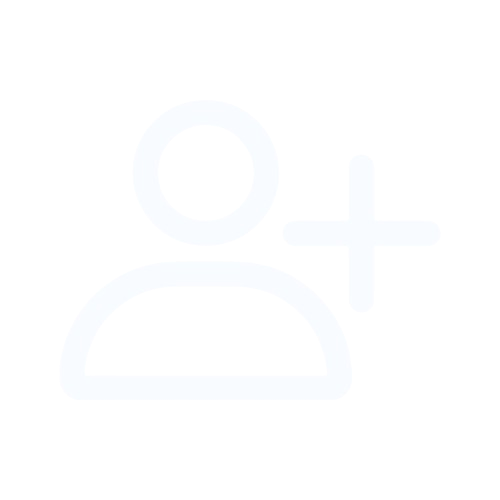2025年2月19日
インフラエンジニアがフリーランスになる方法は?案件獲得方法や単価、必要スキルを解説

フリーランスの働き方には、案件の自由な選択や高単価案件での収入アップなど多くの魅力がありますが、その一方で収入の不安定さや営業活動の必要性、福利厚生がないといったデメリットもあります。
特に、インフラエンジニアとして働く場合、クライアントのトラブル対応や常駐案件の多さなど、特有の課題への直面も少なくありません。
本記事では、インフラエンジニアがフリーランスとして成功するために必要な情報を、公的データや現場の実情を交えながら詳しく解説します。
[TOC]
インフラエンジニアがフリーランスになることは可能!
ここでは、インフラエンジニアがフリーランスとして活躍できる理由を、公的なデータを活用して具体的に解説します。
フリーランスインフラエンジニアの需要は年々増加している
経済産業省の資料では、日本ではIT人材不足が深刻化しており、2030年には約79万人の人材不足が予測されています。この背景には、クラウド技術やサイバーセキュリティ需要の急増があります。
参考:経済産業省
インフラエンジニアは、IT基盤を支える重要な役割を担っており、特にクラウドサービスの普及やデジタル化の推進において必要不可欠な存在です。企業のIT基盤を支えるインフラエンジニアへの需要は、今後も継続的に拡大する可能性が高いと言えるでしょう。
クラウドサービス市場の拡大
総務省の調査によると、日本のパブリッククラウドサービス市場は2023年に3兆1,355億円に達し、前年から25.8%の増加を記録しました。この市場は今後も急速に成長を続け、2028年には6兆5,146億円規模に達すると予測されています。
参考:総務省
クラウド市場の成長により、AWSやAzure、GCPなどの主要クラウドプラットフォームを活用した案件が増加しており、フリーランスインフラエンジニアが関与する機会も増えています。
2025年の崖問題回避が急務
経済産業省は、2025年の崖問題について危機感を持っています。
2025年の崖とは、日本国内の基幹システムの多くが老朽化し、更新が間に合わないことで生じる経済的損失を指しますが、これはすでに現実の課題となっています。
多くの企業が、システム更新やクラウドへの移行を急ピッチで進めているものの、必要なエンジニアの人材不足に直面しており、課題解決が遅れています。
参考:経済産業省
このような状況下で、フリーランスのインフラエンジニアが活躍できる場は多岐にわたります。
例えば、基幹システムのクラウド移行支援が活発化しており、既存システムをクラウド環境へ移行することで維持管理コストの削減が図られています。
また、セキュリティリスクの高まりに対応するため、ファイアウォールの設計やアクセス制御の強化も進められています。さらに、システム運用の自動化を導入することで、人的コストの削減を目指す動きも見られます。
しかし、既存の人員だけでは対応が難しく、人手不足の状態が続いているため、フリーランスのインフラエンジニアの力を借りる必要性が高まっています。
インフラエンジニアの平均年収や単価
ここでは、会社員とフリーランスのインフラエンジニアにおける収入の違いについて、公的データや信頼性のある情報をもとに解説します。
会社員インフラエンジニアの平均年収
厚生労働省によると、会社員インフラエンジニアの平均年収は約684万円となっています。
参考:厚生労働省
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/318
また、国税庁の調査によると令和5年分の給与所得者全体の平均給与は460万円です。
インフラエンジニアの給与は平均的な給与所得者よりも200万円以上高いです。
会社員の中だけで比較してもかなり恵まれた待遇を得ている人が多い傾向にあると言えるでしょう。
フリーランスインフラエンジニアの単価
フリーランスインフラエンジニアとして働く場合、単価は経験やスキル、案件の種類に大きく依存します。
相場感は、一般的には月額50万円から90万円以上が相場とされています。高い専門性やリーダーポジションを任される案件では、単価がさらに高くなることもあります。
以下は、ランサーズエージェントで公開されているインフラエンジニア案件の例です。単価や業務内容を簡潔に記載しています。
| 案件 | 単価(月額) | 業務内容 | 勤務地 |
| 水道管システムクラウドサービス | 50万円 | AWSを用いたクラウドサービスの運用テスト・検証等 | 渋谷・新宿 |
| セキュリティSaaS事業の基盤構築 | 94万円 | AWSを活用したセキュリティ基盤の設計・運用等 | 品川 |
| データウェアハウス移管支援 | 47万円 | オンプレミスからAWS Redshiftへの移行 | 紀尾井町 |
| モバイル向けWebアプリインフラ設計 | 79万円 | AWS環境下におけるインフラ設計や構築等 | リモート相談可能 |
参考:ランサーズエージェント
https://tech-agent.lancers.jp/project
単価には少しバラツキがあるものの、比較的、高単価な案件が多い傾向にあると言えます。
インフラエンジニアの働き方を開発系エンジニアと比較する
インフラエンジニアと開発系エンジニアでは、働き方や業務内容が大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。
働き方の違い
インフラエンジニアと開発系エンジニアの働き方を比較した表は、以下の通りです。
| 項目 | インフラエンジニア | 開発系エンジニア |
| 主な働き方 | システムの基盤構築や運用管理 | アプリケーションやソフトウェアの開発 |
| 労働時間の特徴 | トラブル対応で深夜や休日の作業発生もある | プロジェクトごとに納期が決まるが比較的柔軟な働き方が可能 |
| リモートの可能性 | 常駐が多い(リモート案件も増加中) | リモートワーク案件が多い |
案件の違い
インフラエンジニアと開発系エンジニアの案件の違いは、以下の通りです。
| 項目 | インフラエンジニア | 開発系エンジニア |
| 案件の種類 | サーバー構築、クラウド移行、ネットワーク設計、セキュリティ対策 | ウェブアプリケーション、モバイルアプリ、業務システムの開発 |
| 案件規模 | 大規模システムや基幹業務システムの案件が多い | 小規模から大規模まで幅広い |
| 単価 | 高単価(50万~100万円以上/月が相場) | 幅広い(30万~80万円以上/月が相場) |
単価相場に関してはその時々に応じて変化するため、あくまでも目安として参考にしてください。
常駐案件が多い傾向
インフラエンジニアはシステム環境の構築や運用をするため、現場に直接常駐する案件が多い傾向があります。しかし近年では、クラウドサービスの普及により、リモートワーク可能な案件も増加しています。
一方、開発系エンジニアはツールやリモート環境を活用して作業できるため、リモート案件が主流になりつつあります。
プロジェクトの責任範囲が広い
インフラエンジニアの責任範囲が広い理由は、以下のような特性や役割に起因します。
以下に、その特性や役割について解説していきます。
関係者が多い
インフラエンジニアは、プロジェクトの基盤となるシステム環境を整備するため、さまざまな関係者との連携が必要です。
例えば、以下のようなチームや部門と調整をします。
インフラエンジニアは、さまざまなチームと連携しながらシステム環境を構築・維持していきます。開発チームとは、アプリケーションが円滑に動作する環境を提供するために協力し、開発要件に応じたサーバーやネットワークの設計を行います。
また、セキュリティチームとは、システムの安全性を確保するために連携し、ファイアウォールの設定やアクセス制御の要件を満たすことが求められます。
さらに、発注企業の現場担当者と連携する運用部門とも密接に関わります。構築したインフラを円滑に運用・保守できるよう、ドキュメントや手順書を整備することが重要です。
現場の担当者に適切に説明できなければ、認識のズレから衝突が生じる可能性もあるため、状況に応じた配慮が必要になります。
発注元の現場にはさまざまな職種の従業員がいるため、スムーズな調整のためにはコミュニケーション能力が求められる場面も少なくありません。
ただし、多くの場合、ITの専門家としての立場を尊重して接してもらえるため、技術的に可能なことと不可能なことを誠意をもって伝えれば、協力を得られることが多いでしょう。
プロジェクト全体への影響が大きい
インフラは、システム全体の「基盤」であり、プロジェクト全体の成功や失敗に直結します。例えば、サーバーやネットワークが不安定であれば、アプリケーションの動作に影響を与え、プロジェクト全体が遅延する可能性があります。
トラブル発生時の責任を負う
システムトラブルが発生した場合、インフラエンジニアが最初に呼び出され、問題の一次対応をします。その後、必要に応じて開発チームや外部ベンダーと連携して根本原因の特定や復旧作業をします。
トラブル対応の頻度が高い場合、24時間体制でオンコール対応を求められることもあります。また、影響範囲が広い場合には、迅速な関係者への報告や調整が必要で、非常に負担が大きい役割です。
ただし、これは会社員エンジニアとして勤務する場合であり、フリーランスの場合には対応しなければならないケースは非常に少ない傾向にあります。
理由として、フリーランスは作業量や業務内容、拘束時間などによってその単価が定められており、また、契約内容を超えた要求は断ることができるからです。
仮に発注主が、正社員と同じようにフリーランスエンジニアを24時間拘束したとすれば、月当たり数百万円の追加料金を請求される可能性が高いです。
さらにいえばそのような要求は断られ、最初から契約されない可能性もあります。
このようにフリーランスとしてインフラエンジニアをする場合、24時間のオンコール体制を要求される可能性は低いと言えます。
フリーランスインフラエンジニアのメリット
ここでは、フリーランスインフラエンジニアだからこそ得られる働き方や利点について、具体例を交えながら解説します。
自分で案件を選択できる
フリーランスの大きな魅力は、自分のスキルや興味に合った案件を自由に選べる点です。
例えば、クラウド環境の移行プロジェクトやセキュリティ強化対応など、自身の得意分野に特化した案件を選ぶことで、スキルを最大限に活かすことができます。
また、稼働日数や働き方も柔軟に調整可能です。週3日稼働の案件を選んでプライベートの時間を確保したり、短期案件でスキルアップを図ることもできます。
高単価案件で年収アップが狙える
フリーランスインフラエンジニアは、正社員に比べて高単価の案件を受注しやすい傾向があります。
特に、AWSやAzureを用いたクラウド構築や、大規模なネットワーク設計といった専門性の高い案件では、月単価が80万円以上になることもあります。
さらに、単価交渉が直接可能であるため、スキルや実績次第ではさらに高額な報酬を得ることができます。
スキルに応じて多様なプロジェクトに参加できる
フリーランスの利点の一つは、幅広い業界やプロジェクトに携われる点です。
例えば、製造業のIoT基盤構築、金融業界のセキュリティ強化、様々な業界のクラウド移行支援など、多様な分野で経験を積むことができます。
これにより、専門スキルを磨くと同時に、自身の市場価値を高めることが可能です。
リモート案件も増えており、在宅勤務が可能
近年、リモートワーク対応の案件が増えているため、場所にとらわれない働き方が可能になっています。
例えば、地方在住でも東京や大阪にある大企業の案件の担当ができ、通勤のストレスや時間を削減できます。また、育児や介護と両立しながら働ける環境の構築もできます。
正社員時代のような上司・部下の関係がなくなる
フリーランスでは、業務成果に焦点が当てられるため、正社員特有の上下関係や煩わしい人間関係から解放されます。
正社員時代は縦の関係が重視されてきましたが、フリーランスは様々な取引先と対等な関係に立つ横の関係性の構築の方が重要なのです。
具体的な例としては、無駄な会議や社内政治に関わる必要がなく、業務効率が向上する点が挙げられます。
直接クライアントとやり取りできるため、余計な調整業務が減り、ストレスの軽減につながります。さらに、上司と部下といった組織内の上下関係に縛られることなく、クライアントに対して丁寧にコミットすることで、成果に応じた収入増も期待できます。
インフラエンジニアとして働く場合、常駐先の従業員とやり取りする機会はあるものの、上司と部下といった関係がないため、人間関係のストレスを感じにくい環境で勤務できる点もメリットの一つです。
また、インフラエンジニアの場合はクライアントからの評判を得るにあたって、リモートでない限りは直接滞在先の従業員との接触も多くなるため良い評判が得られた場合、好条件のオファーや継続依頼が受けられる確率が高くなります。
例えば、大企業の基幹プロジェクト(生産管理システムや会計システム等)に参加する場合、そこの現場スタッフに懇切に接しましょう。
人柄が良く技術力もあるという評判になれば、再度依頼が来る可能性が高くなるのです。
人間関係において顧客を最優先する姿勢がフリーランスを成功に導きます。
実績を積めば営業活動をしなくても案件を得やすい
フリーランス初期は案件獲得のために営業活動が必要ですが、実績が増えるにつれ、リピート依頼や紹介案件が増えていきます。
例えば、大企業のクラウド移行プロジェクトを成功させた実績が、別のクライアントからの新たな依頼につながるケースがあります。
また、一度エージェント経由で案件を担当した企業から、リピートオファーを受けることも少なくありません。こうした実績を積み重ねることで、自分から積極的に営業しなくても、安定して案件を獲得できるようになります。
しかし、常に新しい案件を意識し、アピールや営業活動を怠らないことが重要です。特に売上が安定しているときほど、次の案件を確保するための動きが欠かせません。
案件がなくなってから営業を始めるのでは遅いため、仕事が忙しく余裕がないと感じるくらいの段階で、新たな案件獲得に向けた行動を習慣化しておくことが大切です。
得意な分野に集中して仕事ができる
フリーランスでは、自分の強みを活かせる分野に特化した案件を選ぶことができます。
例えば、クラウド技術やセキュリティへの特化によって、より高度な案件に取り組む機会が増えます。
これにより、専門性を高めながら、さらに高単価な案件を継続的に受注可能です。
フリーランスインフラエンジニアのデメリット
フリーランスとして働くインフラエンジニアには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットや課題も存在します。ここでは、それらを具体的に解説します。
収入が安定しない
フリーランスにとって最も大きなリスクの一つが、収入の不安定さです。案件の有無に応じて収入が大きく変動するため、長期的な経済的安定を確保するのが難しい場合があります。
具体的には、プロジェクトが終了した後、次の案件を獲得するまでに数週間から数か月の空白期間が生じる可能性があります。また、クライアントの都合で契約が急遽終了し、予定していた収入が突然途絶えるリスクも考えられます。
こうした事態に備えるためには、いくつかの対策が必要です。まず、複数の案件を並行して受注し、収入源を分散することでリスクを軽減できます。また、収入がない期間に備え、生活費の3〜6か月分を貯蓄しておくことも重要です。余裕があれば1年分以上の貯蓄を確保しておくと、より安心して仕事を続けられるでしょう。
ただし、インフラエンジニアの場合は常駐案件かつ長期案件も多い傾向にあり、開発系のフリーランスエンジニアよりも若干安定度は高いと言えます。
また、普段から少し節約をして、貯金をする習慣をつけましょう。サラリーマン時代とは異なり、毎月必ず収入が発生するとは限りません。フリーランスは、万が一の時の備えを常にしておくことが重要なのです。
社会的信用が下がる
フリーランスで働くと、正社員に比べて社会的信用が低いと見なされることがあります。特に、ローン審査や賃貸契約で不利になることが多いです。
例えば、フリーランスであることを理由に住宅ローンの審査が通らなかったり、賃貸契約時に一定の貯蓄があることを証明するために残高証明書の提出を求められるケースがあります。また、青色申告控除や専従者給与の支払いによって所得金額が低く見積もられることで、賃貸契約や住宅ローンの審査が通りにくくなることもあります。さらに、クレジットカードの発行を断られる場合も少なくありません。
こうした問題への対策としては、過度な節税を避け、適正な所得金額を確定申告で計上することが重要です。また、住宅ローンを検討している場合は、フリーランスになる前に正社員のうちに契約を済ませておくのも一つの方法です。
ただし、所得金額が高くなると税金が高額になることや、正社員時代にローンを組んでも、フリーランスになってから収入が下がり、返済金額が高すぎれば結局返済できません。
特に住宅ローンについては、都会では非常に高額になる傾向のため、慎重に考えて決断するようにしてください。
あまりに高すぎる住宅ローンは、住む場所を固定化してしまいます。
クレジットカードに関してはフリーランス向けのクレジットカードを発行している会社もあります。
こちらはそれほど苦戦しないでしょう。
案件獲得のための営業活動が必要
フリーランスでは、自分で案件を探し、契約を結ぶための営業活動が必須です。特にフリーランスとしてのキャリア初期には、実績が少ないため苦労してしまうことが多いです。
具体的には、案件を獲得するために複数のエージェントに登録し、時間をかけて営業活動を行う必要があります。また、クライアントとの交渉や提案資料の作成といった業務も求められるため、技術力だけでなく、コミュニケーションやプレゼンテーションといったスキルも必要になります。
さらに、営業をかけたからといって必ずしも案件が成約するとは限らず、不確実性と向き合いながら仕事を進めていくことが求められます。
対策は、以下の通りです。
- 専門のフリーランスエージェントを活用して案件を効率的に探す。
- ITエンジニアに特化したフリーランスエージェントがおすすめです。
- 自分のポートフォリオサイトを作成し、実績をアピール。
- 特に自分の名刺代わりとなるWEBサイトを独自ドメインで一つ作ることをおすすめします。
- 受注できた顧客の特徴や企業規模をしっかりとデータ化
自分の性格やスキルと相性の良い顧客の傾向を把握して、営業成約率を高める努力をしましょう。
対策として、まず専門のフリーランスエージェントを活用することで、効率的に案件を探すことができます。特に、ITエンジニア向けのフリーランスエージェントを利用すると、より自分に適した案件を見つけやすくなります。
また、自分の実績をアピールするために、ポートフォリオサイトを作成するのも効果的です。特に、独自ドメインでWebサイトを持つことで、名刺代わりとして活用でき、クライアントに対して信頼性を高めることができます。
さらに、受注できた顧客の特徴や企業規模をデータ化し、自分のスキルや性格と相性の良いクライアントの傾向を把握することも重要です。これにより、より成約率の高い営業活動が可能になり、無駄なアプローチを減らすことができます。
税務処理という雑務が増える
フリーランスは、確定申告(会社員時代は年末調整として勤務先企業が代行)のように、これまで会社がしてくれた業務にすべて自分で対応する必要があります。
例えば、毎年の確定申告では、経費や収入を正確に計算し、適切に申告する必要があります。これまで会社が代行していた控除などの手続きを、自分で理解し対応しなければならないため、事務処理の負担が増える点が課題となります。
この負担を軽減するためには、会計ソフトや税理士を活用するのが有効です。会計ソフトは月額1,600円程度で利用でき、確定申告のみを税理士に依頼する場合、単発で7万円程度の費用で対応してもらえるケースもあります。
また、業務が本格的に忙しくなり、利益が安定してきたら、顧問契約を結び、確定申告を一任できる税理士を探すのも選択肢の一つです。一般的には、売上が1,000万円を超えるあたりで顧問税理士が必要になることが多いため、そのタイミングを目安に検討するとよいでしょう。
トラブル対応をすべて自分でする必要がある
クライアントとの契約上のトラブルや、システム障害時の対応はすべて自分でする必要があります。
例えば、契約内容の解釈を巡ってクライアントと意見が対立し、追加作業を無償で求められるケースがあります。
システム障害が発生した際に、緊急対応を一人で行わなければならず、負担が大きくなることも考えられます。こうしたトラブルを防ぐためには、まず契約書を詳細に作成し、業務範囲を明確にしておくことが重要です。
また、緊急時の対応方針や連絡体制を事前にクライアントと共有し、対応のルールを決めておくことで、想定外の負担を減らせます。
特に、緊急時の時間外対応を含め、すべてのケースを想定した契約書の締結や見積もりの提示が必要です。あらかじめ具体的な見積もりを出すのが難しい場合は、「契約時間外の対応は1時間いくら」といった形で料金を設定するのも有効な方法です。
契約で取り決めのない作業は、基本的にフリーランス側のリスクとなるため、業務範囲や料金体系を明確にし、クライアントとしっかり共有しておくことが、円滑な取引につながります。
正社員時代のような福利厚生がない
フリーランスには、正社員時代に受けていた福利厚生(退職金や有給休暇、健康診断など)がありません。そのため、自分でこれらを補完する必要があります。
フリーランスとして働く上で、病気やケガによって仕事ができなくなった場合、収入が途絶えるリスクがあります。また、健康診断や自己啓発にかかる費用はすべて自己負担となるため、長期的なキャリアを考えるうえで負担が大きくなる可能性があります。
これに対する対策として、まずフリーランス向けの所得補償保険や医療保険に加入し、万が一の事態に備えることが重要です。また、健康を維持するために、年に1回は健康診断を受けるなど、自己管理を徹底することも欠かせません。
さらに、勉強代補助制度を提供しているフリーランスエージェントを活用することで、スキルアップにかかる費用負担を軽減することも可能です。こうした対策を講じることで、健康リスクやキャリアの停滞を防ぎ、安定した働き方を維持しやすくなります。
孤独感を感じることがある
フリーランスは、会社員時代のようなチーム環境がない(同僚がいない)ため、孤独感を抱えることがあります。
例えば、リモートワーク中心の働き方では、人と直接会う機会が少なくなり、孤独を感じやすくなります。また、技術的な問題に直面した際に相談できる同僚がいないことで、解決までに時間がかかることもあります。
仕事の愚痴を話したり、気軽に会話できる相手がいないことも、精神的な負担につながることがあります。
このような状況を防ぐためには、フリーランス向けのコミュニティや勉強会に参加し、他のエンジニアとつながることが有効です。また、エージェントが主催するイベントやセミナーに積極的に参加することで、仕事仲間を作る機会を増やすことができます。
さらに、客先常駐案件を請けることで、現場の社員と食堂や休憩所などで会話する機会が生まれ、孤独感を和らげることができます。ただし、常駐先の社員はクライアントでもあるため、適切な距離感を保ち、礼節をわきまえた対応を心がけることが大切です。
インフラエンジニアの仕事内容
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤を支える重要な役割を担っています。その仕事は多岐にわたり、設計から構築、運用、そして保守まで幅広く関わります。ここでは、インフラエンジニアの具体的な仕事内容を深掘りして解説します。
設計
設計業務は、インフラエンジニアにとってシステムの基盤を構築するうえで欠かせない重要なフェーズです。具体的には、まずサーバーやネットワークの構成を検討し、システムがスムーズに動作するように、どこにどのようなサーバーや機器を配置するかを計画します。
また、クラウド環境の導入計画も設計業務の一環です。企業がデータを保存したり、アプリケーションを運用したりするために、どのクラウドサービスをどのように活用するかを決定します。
さらに、トラフィック量や負荷を考慮した設計も重要な要素です。システムにどれだけのデータやアクセスが集中するかを予測し、それに耐えられる構成を整えることで、安定した運用を実現します。
これらの業務は、システム全体が安定して稼働するための「設計図」を描くような役割を果たしており、インフラエンジニアのスキルが問われる分野の一つです。
構築
構築とは、設計したシステムを実際に形にする作業のことであり、インフラエンジニアの技術力が最も試されるフェーズといえます。この工程では、まずシステムを動作させるための土台となるサーバーをセットアップし、適切な環境を整えます。
次に、システム同士がスムーズに通信できるよう、ネットワーク機器の設定を行い、安全かつ効率的な通信環境を構築します。また、クラウドサービスを活用し、データの保存やアプリケーションの稼働環境を整備する作業も重要な業務の一つです。
これらの業務を適切に遂行することで、設計通りのシステム環境が実現され、安定した運用につながります。
運用と保守
運用と保守は、インフラエンジニアの業務の中でも最も長期的かつ重要な役割を担います。このフェーズでは、システムが計画通りに稼働しているかを常に監視し、安定した運用を維持することが求められます。
また、障害が発生した際には、迅速に原因を特定し、適切な対応を行うことが不可欠です。システムの安定稼働を継続させるためには、定期的なメンテナンスも重要であり、計画的に点検や更新を行うことで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
例えば、ECサイトの運営では、24時間365日アクセス状況やサーバー負荷を監視し、異常が発生した場合には即座にアラートを受け取り、迅速に対応するといった業務が求められます。
セキュリティ管理
セキュリティ管理もインフラエンジニアにとって重要な業務の一つです。近年、サイバー攻撃の増加に伴い、システムの安全性を確保するための対策がますます求められています。
具体的には、システムを不正アクセスや外部からの攻撃から守るために、ファイアウォールの設定を適切に行うことが必要です。また、組織のセキュリティ基準を定め、それを日常業務に反映させることで、リスクを最小限に抑えます。
さらに、万が一データが破損したり消失した場合に備え、バックアップの取得や復旧計画を整備することも欠かせません。こうした取り組みによって、システムの安全性と安定性を高め、企業の事業継続を支えることができます。
ドキュメント作成
ドキュメント作成は、インフラエンジニアの業務の中で見落とされがちですが、プロジェクトの成功や円滑な引き継ぎに欠かせない重要な作業です。
具体的には、システムの設計書や構築手順書を作成し、どのような構成でシステムが設計・構築されたのかを明確に記録します。また、運用マニュアルを整備し、システムの管理やトラブル対応の手順をわかりやすくまとめることで、運用チームやクライアントが適切に対応できるようにします。
さらに、障害発生時の対応履歴を記録し、問題が再発した際に迅速な原因特定と対策ができるようにすることも重要です。例えば、クライアントが社内で運用を継続できるよう、システム構築手順を詳細に記載したドキュメントを作成したり、引き継ぎ時にはすべての設定内容を記録した資料を提供したりすることで、スムーズな運用を支援します。
適切なドキュメントを作成することで、業務の属人化を防ぎ、長期的なシステムの安定運用につなげることができます。
インフラエンジニアに必要なスキル
インフラエンジニアとして成功するためには、多岐にわたる技術的スキルと、クライアントやチームメンバーとの連携を可能にするソフトスキルが求められます。ここでは、フリーランスとして特に重要なスキルを具体的に解説します。
クラウドスキル(AWS、Azure、GCP)
クラウドコンピューティングは、現代のインフラエンジニアにとって欠かせないスキルの一つです。近年、多くの企業がオンプレミス環境から AWS、Azure、GCP などのクラウド環境へ移行しており、それに伴いクラウド環境の構築や運用スキルの重要性が高まっています。
クラウドの活用によって、システムの柔軟性や拡張性が向上し、コストの最適化も可能になります。そのため、インフラエンジニアには、クラウドサービスの特性を理解し、適切な環境を設計・構築できるスキルが求められます。また、セキュリティ設定や運用管理の知識も不可欠であり、クラウドを活用したシステムの安定運用に貢献することが期待されます。
サーバー管理スキル
サーバーの構築や運用スキルは、インフラエンジニアにとって基礎となる重要な能力です。企業のシステムはサーバーの安定稼働に依存しており、その管理を担うのがインフラエンジニアの役割だからです。
例えば、サーバー障害やデータ損失に備えて、定期的なバックアップの設定を行い、トラブル発生時にデータを迅速に復旧できる環境を整えます。また、障害時の影響を最小限に抑えるため、適切なリカバリ手順を確立し、短時間での復旧が可能となるよう準備しておくことも欠かせません。
サーバーの安定運用を支えるためには、パフォーマンスの監視や負荷分散、セキュリティ対策など、多岐にわたる知識と経験が求められます。そのため、インフラエンジニアは常に最新の技術や運用手法を学びながら、サーバー環境の最適化に努める必要があります。
ネットワーク設計や構築スキル
インフラエンジニアは、ネットワーク環境の設計と構築スキルが必要です。システム間の通信を最適化し、ネットワークの安全性確保は、システム全体のパフォーマンスに直結します。
例えば、地理的に離れた複数のオフィスやデータセンター間を安全に接続するネットワークを設計・構築します。
セキュリティ知識
セキュリティ知識はインフラエンジニアにとって必須のスキルとなっています。なぜなら、サイバー攻撃が増加傾向にあるからです。
システムの脆弱性を放置すれば、データ漏洩やサービス停止といった重大なリスクが発生します。セキュリティログの監視と脅威の早期検出や、ファイアウォールなどによる対策が必要となります。
コミュニケーション能力
インフラエンジニアは、技術スキルだけでなく、関係者との効果的な連携をするためのコミュニケーション能力も重要です。理由としては、クライアントや開発チーム、運用担当者と協力し、スムーズにプロジェクトを進行させるためには適切な説明と調整が必要だからです。
例えば、クライアントに技術的な提案をわかりやすく説明し、開発チームと要件を共有し、システム要件の正確な理解が必要です。
また、障害発生時の迅速な情報共有と対応にもコミュニケーション能力が必要となります。
【重要】営業力!案件獲得のための必須スキル
フリーランスとして働く場合、自分自身で案件を獲得する営業力が不可欠です。なぜなら、案件がなければ収入が途絶えてしまうからです。会社員時代とは異なり、案件がなくなれば即座に収入がなくなるのです。営業活動は生存戦略の一部といえます。
仮に安定的な収入が得られる状態を作れたとしても、常に新しい仕事を探す意識は持ってください。
ただし、あまりにも仕事のことばかりを考えていると精神的にも肉体的にも疲れます。
営業のことを意識しつつも、趣味を持ち、積極的にリフレッシュの時間を作って、疲れないような工夫をしましょう。
また、フリーランスエージェントへの登録によって案件が途切れるリスクを減らすことができます。
プロジェクト管理能力!複数案件の同時進行に必要
複数のプロジェクトを効率的に進めるためのプロジェクト管理能力も重要です。理由として、フリーランスは、複数のクライアントと並行してのプロジェクト進行が一般的だからです。
タスク管理ツールやメモでも良いのでto doリストを作り、優先順位をつけて仕事を処理していくようにしましょう。
フリーランスになる前に準備すべきこと
フリーランスインフラエンジニアとして成功するためには、準備が重要です。ここでは、フリーランスになる前にするべき具体的な準備を解説します。
実務経験を積む
フリーランスとしてインフラエンジニアが案件を獲得するには、十分な実務経験が不可欠です。企業は即戦力を求めるため、経験が不足していると案件の受注が難しくなる可能性があります。
一般的には、5〜10年程度の実務経験を積むことで、フリーランスとして活躍できるスキルセットが身につくとされています。
この期間中に、設計や構築といった上流工程の経験を積むことが重要です。例えば、大規模プロジェクトでサーバー設計を担当したり、クラウド移行プロジェクトでリーダーを務めた経験があれば、クライアントからの信頼を得やすくなります。
また、現在の職場で必要なスキルが身につかない場合は、転職を検討するのも一つの方法です。クラウド技術やセキュリティ対策などの市場価値の高いスキルを得られる環境で経験を積むことで、独立後の選択肢が広がります。必要なスキルを計画的に習得しながら、フリーランスとしての基盤を築きましょう。
スキルの棚卸し
自分のスキルを客観的に把握し、市場での強みを明確にする必要があります。クライアントに自分を売り込むためには、自分自身のスキルを理解している必要性があるからです。
過去のプロジェクトを振り返り、担当した業務や習得したスキルをリストアップします。特に強みとなる分野(例えば、クラウド構築、セキュリティ設計など)を明確にしましょう。
また、このスキルの棚卸では、自信をつけるということも大切です。
「これだけ経験を積んで頑張ってきたのだから、フリーランスになってもやっていける」と言えるだけの経験があれば自然と独立も前向きに検討できるでしょう。
契約書の作成方法を学ぶ
フリーランスでは、契約書がトラブル防止の要となります。契約書がなければ、ほぼ口約束で仕事を請けてしまった状態となります。
口約束でも契約は成立しますが、口頭契約はトラブルが起こりやすいので紙に書いて合意を取り付ける必要性があるのです。
例えば、契約する頻度の比較的高いNDA(秘密保持契約)や業務委託契約書の基本項目、法的効力の確認方法などを勉強しましょう。
NDAであれば具体的にどのような情報を秘密にしたいのか、期間は不当に長くないかを確認してください。頻繁に契約するクライアントと1年単位で守秘義務契約を結ぶことは悪いことではありません。一方で、単発で仕事が終わるクライアントと1年単位の守秘義務を結ぶのは長すぎて不適当なことがあります。
業務委託契約書では、支払い期間や、支払いの条件について確認しましょう。最もトラブルになりやすいのは報酬の未払いです。
納品してから何日後に報酬を支払うのかなど、正確に記載するようにしましょう。
税務処理の基礎知識をつける
フリーランスとして働く場合、税務処理はすべて自分で対応しなければなりません。税務知識が不十分なままでは、誤った申告や不要な税金の支払いにつながる可能性があります。そのため、最低限の基礎知識を身につけておくことが重要です。
まず、経費計上のルールを理解することが必要です。事業に必要な支出を適切に経費として計上することで、節税につながります。例えば、交通費、通信費、書籍代、研修費、クラウドサービスの利用料などが経費として認められますが、どこまでが適用されるのかを事前に把握しておくことが大切です。
次に、勘定科目の知識も押さえておくべきポイントです。勘定科目は経費を分類するための項目で、例えば10万円以下のパソコン購入費用は「消耗品費」として計上されます。このルールを理解しておくことで、正確な帳簿作成が可能になります。
さらに、青色申告のメリットを活用することで、節税効果を最大化できます。青色申告を行うことで、最大65万円の控除が受けられるため、フリーランスにとって非常に有利です。ただし、複式簿記での記帳が必要になるため、freeeや弥生会計といった会計ソフトを活用すると、より効率的に管理できます。
最後に、確定申告の流れを把握しておくことも欠かせません。
確定申告は毎年2〜3月中旬に提出する必要があり、収支内訳書や必要経費の記録を整理しておく必要があります。特に「収入」と「経費」を明確に分け、領収書や契約書を適切に保管する習慣をつけておくと、申告時の手続きがスムーズになります。
こうした基礎知識を身につけることで、税務処理の負担を減らし、適切な節税対策を行うことができます。
社会保険・年金の切り替え
フリーランスになると、会社員時代の健康保険や厚生年金から国民健康保険と国民年金に切り替える必要があります。
国民年金への切り替え
会社を退職すると、年金事務所に会社から資格喪失届が提出されます。年金に関してはそれで自動的に切り替えとなり、住民票上の住所地に国民年金保険料の請求書が来ます。手続きは特にありません。
健康保険は国民健康保険に切り替える
会社を辞めたあとは、原則として、国民健康保険に加入が必要です。国民健康保険料は所得に応じて料金が決まり、また、少子高齢化で保険料を支払う現役世帯が減少傾向にあるため、会社員時代よりも重い負担になる可能性が高いです。
ただし、健康保険に関しては、任意継続被保険者制度があります。
健康保険の任意継続
国民健康保険料の負担が大きくなる場合、会社員を辞める前に、前の会社で加入していた健康保険組合で任意継続をしましょう。2ヶ月以上勤務していた場合に加入できます。金額が一定になり、2年間使え
ます。退職後20日以内に手続きをするようにしてください。
参考:協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/
おすすめの方法は、一旦、任意継続被保険者になることです。その後改めて住民票を管轄する区役所に行けば、料金がいくらくらいかを教えてくれます。
任意継続被保険者制度は退職後20日を経過すれば加入できなくなりますが、国保はいつでも加入できます。
先に任意継続して、あとで確認して国保の方が料金が安ければ国保に加入すれば良いです。
リスク管理の重要性を理解する
リスク管理はフリーランスにとって、とても大切です。
キャッシュフロー管理
収入が不規則なフリーランスにとって、キャッシュフローの管理は重要です。計画的な支出管理と貯蓄がリスクを軽減します。
例えば、案件ごとの収入予測を立て、必要経費や税金の支払い時期を把握しておくようにしましょう。
また、フリーランス特有の季節変動(年度末に案件が増えるなど)を意識して、収入計画を立てることも大切です。
独立したては不安かもしれませんが、独立して2年ほど経過すると、青色申告をしている場合は月ごとの売上を確定申告時に計算する必要性がでるため、自然と把握できるようになります。
ポートフォリオを作成する
フリーランスとしての仕事をスムーズに獲得するためには、自分のスキルや実績をアピールするポートフォリオが欠かせません。
特にインフラエンジニアは、プロジェクトの成果が直接目に見えにくいため、ポートフォリオを通じて具体的な実績を示すことが重要です。
ポートフォリオに含めるべき内容は、以下の通りです。
プロジェクトの概要と役割
「大手ECサイトのクラウド移行プロジェクトで、AWS環境の設計と構築を担当」といった具体的なプロジェクト内容を明記します。
成果を数値で示す
例えば、「クラウド移行により運用コストを30%削減」や「ネットワーク障害を50%減少させる設計を導入」など、具体的な効果の数値化によって、信頼性が高まります。
使用した技術やツール
AWSやAzureなど使用した技術やツールを明示し、スキルの幅広さをアピールします。
ドキュメント作成の能力
設計書やマニュアルのサンプルの添付によって、実務の中でのドキュメント作成能力を示します。
ポートフォリオはPDFやオンラインポートフォリオ(例えば、SNSや個人Webサイト)としてまとめ、クライアントに簡単に共有できるようにしましょう。
ポートフォリオは、オンライン上にアップロードしておけば、24時間365日営業をしてくれる心強いツールとして機能してくれます。
円満退職を心がける
フリーランスとして新たなキャリアを始める際、現在の職場の円満退職は、トラブルを防ぎ、今後のキャリアにプラスとなる人脈を維持する上で重要です。
フリーランスとして独立する前に、退職の準備をしっかりと進めることが大切です。スムーズな退職ができるよう、以下のポイントを押さえておきましょう。
まず、退職の意思は早めに伝える ことが重要です。一般的に、退職の1〜3ヶ月前には上司に意向を伝えるのが適切とされています。早めに伝えることで、業務の引き継ぎや整理がスムーズに進み、職場に迷惑を
まず、退職の意思は早めに伝える ことが重要です。一般的に、退職の1〜3ヶ月前には上司に意向を伝えるのが適切とされています。早めに伝えることで、業務の引き継ぎや整理がスムーズに進み、職場に迷惑をかけることなく円満退職しやすくなります。
また、上司の頭を飛び越えずに報告する ことも大切です。退職の意向は、必ず直属の上司(課長など)に伝え、順序を守るようにしましょう。突然、人事や社長に直接報告すると、上司との関係が悪化する可能性があるため、慎重に進めることが求められます。
引き継ぎを丁寧に行う ことも欠かせません。後任者がスムーズに業務を進められるよう、手順書やドキュメントを整理し、「どの業務に誰が関わっているのか」「どのツールを使うのか」などの具体的な情報を明確に伝えることが重要です。特に近年では、適切な引き継ぎを怠った結果、企業側から損害賠償請求を受けるケースも報告されています。
退職後も良好な関係を維持したいと考えている場合は、引き継ぎにしっかりと取り組むことで、前職とのつながりを活かしながらスムーズにキャリアを進めることができます。
フリーランスの健康管理の重要性
フリーランスとして働くインフラエンジニアにとって、健康管理は長期的なキャリアを築くうえで欠かせません。
フリーランスは正社員と異なり、自己管理が求められる働き方であるため、日々の健康管理が仕事のパフォーマンスに直結します。ここでは、健康を維持するための具体的な取り組みを解説します。
長時間労働を避ける
フリーランスは案件数に収入が直結するため、つい過剰に働いてしまう傾向があります。しかし、長時間労働は集中力の低下や健康リスクを引き起こし、結果的に仕事の質を損なう原因になります。
そのため、1日の労働時間を8時間以内に設定し、優先順位を明確にし、効率的に作業を進めることが求められます。タスク管理ツールを使って作業内容を整理し、1時間作業したら5〜10分の休憩を挟む「ポモドーロ・テクニック」の活用によって、効率的かつ健康的な働き方を実現できます。
近年では、アップルウォッチなどのスマートウォッチ活用で、作業時間や休憩時間を効果的に管理できます。例えば、1時間ごとに休憩を促すリマインダー機能を使うことで、適切なタイミングで休む習慣を作ることが可能です。また、心拍数モニタリング機能で、ストレスや疲労が溜まっていないかのチェックが可能です。
メンタルヘルスケアを積極的にする
フリーランスは孤独を感じやすく、ストレスや不安に直面しがちです。メンタルヘルスを維持するためには、自分に合ったリフレッシュ方法を取り入れることが大切です。
瞑想アプリを使ったマインドフルネスの実践は、ストレス軽減に非常に効果的です。
特に、アップルウォッチを使えば、呼吸法や簡単な瞑想セッションをすぐにでき、忙しいフリーランスの生活に無理なく取り入れられます。
また、リラックス効果のある音楽を聴くことで、集中力を高めることも可能です。
さらに、オンラインコミュニティや業界のイベントに参加し、同業者との交流によって、孤独感を和らげることができます。同時に、仕事に関する新しい情報を得たり、アイデアを共有したりする良い機会にもなります。
適度な運動と生活習慣の見直し
デスクワーク中心の生活では運動不足に陥りやすく、これが体調不良や集中力の低下を招きます。健康を維持するためには、日常的に適度な運動を取り入れることが重要です。
スマートウォッチは、歩数や消費カロリーを記録するだけでなく、アクティビティを促す通知機能も備えています。例えば、1日1万歩を目標に設定し、日々の歩行量の確認によって、運動不足を防げます。また、週2〜3回のジム通いやヨガ、軽いランニングの習慣化によって、さらに効果を高めることができます。
睡眠アプリを使えば、睡眠時間や質を記録して改善のためのヒントを得ることもできます。
さらにいえば、健康的な食事と規則正しい睡眠も重要です。例えば、野菜を多く摂り、タンパク質を適量取り入れる食事を心がけることで、身体的な健康だけでなく集中力や免疫力も向上する可能性があります。
定期的な健康診断の受診
フリーランスは健康診断を受けられないため、自発的に定期健康診断を受ける必要があります。少なくとも年に1回は受診し、身体の状態確認が必要です。
特に、心身に負担がかかる働き方をしている場合、半年ごとの受診を検討するのも良いでしょう。
フリーランスインフラエンジニアに資格は必要なのか?
フリーランスインフラエンジニアとして活躍するためには、実務経験が最も重要視されますが、資格も競争力を高める上で役立ちます。ここでは、特に需要の高い資格とその活用法について解説します。
AWS認定資格
AWS認定資格は、クラウドサービス市場で圧倒的なシェアを持つAmazon Web Services(AWS)の専門知識を証明するものです。クラウド環境への移行や運用を担うプロジェクトでは、AWSのスキルを持つ人材が求められるため、この資格を取得していると案件獲得の幅が広がります。
AWSには、基礎レベルの「クラウドプラクティショナー」から、上級レベルの「ソリューションアーキテクト プロフェッショナル」までさまざまなレベルがあります。たとえば、フリーランスで高単価案件を狙う場合は、「AWSソリューションアーキテクト アソシエイト」以上の資格が効果がある可能性が高いです。
Microsoft Azure資格
Microsoft AzureはAWSに次ぐシェアを持つクラウドプラットフォームであり、企業が採用するクラウド環境として増加傾向にあります。そのため、Azureに関連する資格を持つことで、特にMicrosoft製品を多用する企業の案件に強みを発揮できます。
代表的な資格には「Microsoft Certified Azure Fundamentals」や「Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert」があり、前者は基礎的な知識を、後者は設計や管理の専門知識を証明します。Azureの資格を持つことで、クラウド関連案件で他者と差別化を図れます。
情報処理技術者試験
情報処理技術者試験は、日本国内で広く認知されているIT資格です。特に、ネットワークスペシャリストやデータベーススペシャリストは、インフラエンジニアとしての専門知識を示す上で有効です。
この資格は日本国内での信頼性が高いため、企業に対するアピールポイントとして活用できます。特に、公的機関や大手企業の案件では、これらの資格が有利に働くことがあります。
【要注意】資格は補強材料であり、実務経験が最重要
資格はあくまでスキルの補強材料であり、実務経験には代わることができません。企業がフリーランスに求めるのは即戦力であるため、資格を取得しているだけでは案件を獲得するのは難しい場合があります。
そのため、資格取得に取り組む際は、実務経験と並行してスキルアップを目指すことが重要です。たとえば、クラウド環境のプロジェクトで実務経験を積みながらAWS認定資格を取得するなど、現場でのスキルと資格をリンクさせることで、実績としての信頼性を高めることができます。
フリーランスインフラエンジニアの案件獲得方法
フリーランスインフラエンジニアとして安定的に案件を獲得するためには、さまざまな方法を使い分けることが必要です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、状況やスキルに応じて適切に選ぶことが重要です。
フリーランスエージェントの活用
フリーランスエージェントは、エンジニアと企業の間を仲介するサービスであり、多くの案件を取り扱っています。特に、高単価で長期の案件を探す際に有効な手段となります。
エージェントを利用するメリットとして、まず案件の種類が豊富である点が挙げられます。クラウド環境の構築、セキュリティ対策、運用・保守など、インフラエンジニア向けの多様な案件が揃っているため、自分のスキルや希望に合った仕事を見つけやすくなります。
また、契約や交渉をエージェントが代行してくれるため、案件の単価交渉や契約書作成といった事務作業の負担を軽減できます。さらに、エージェントを経由することで取引の透明性が高まり、未払いリスクが低減するのも大きな利点です。
一方で、デメリットとしては、エージェントに支払う手数料が発生することが挙げられます。一般的に、契約額の10〜30%が手数料として差し引かれることが多いため、実際に手元に残る報酬を事前に確認しておく必要があります。また、案件によっては競争率が高く、希望の仕事を獲得するためには、スキルのアピールや実績の整理が欠かせません。
代表的なフリーランスエージェントには、「ランサーズエージェント」「レバテックフリーランス」「Midworks」などがあり、これらのプラットフォームに登録することで、スキルや経験に応じた案件に参加できるようになります。
直接営業
直接営業は、企業に自らアプローチして案件を獲得する方法です。営業スキルが求められますが、報酬を最大化できる手段でもあります。
メリットとしては、仲介手数料が発生しないため、高単価で契約できる点が挙げられます。また、クライアントとの直接交渉が可能なため、自分の働き方に合わせた条件を設定しやすくなります。信頼関係を構築すれば、リピート案件や長期契約に繋がることも期待できます。
しかし、デメリットもあります。営業活動には時間と労力が必要で、見積書の作成やプレゼンなど、IT分野以外の能力が求められます。また、契約や支払いトラブルが発生した場合、自分で対応しなければならない点もリスクとなります。
クラウドソーシングサイトの活用
クラウドソーシングサイトは、初心者フリーランスでも案件を見つけやすいプラットフォームです。特に副業や短期間での実績作りに向いています。
メリットは、案件に応募しやすく、登録後すぐに利用できる点です。小規模な案件も多いため、経験を積みたいエンジニアにとって良いスタート地点となります。
一方、デメリットとしては、単価が低い案件が多く、高収入を目指すには不向きな場合があります。また、プラットフォームの利用料が発生するため、報酬が減少する可能性もあります。
知人・人脈からの紹介を受ける方法
信頼できる人脈を通じて案件を紹介してもらう方法は、案件獲得の負担を軽減し、安定的に仕事を確保する手段の一つです。
この方法のメリットとして、まず信頼性の高さが挙げられます。紹介元を介した案件は、すでに一定の信頼関係があるため、クライアントとのやり取りがスムーズに進みやすくなります。また、自分から営業しなくても案件が紹介されるため、営業活動の手間を減らすことができます。さらに、紹介案件は一度関係を築くと長期的な取引につながりやすく、継続的に仕事を受注できる可能性が高まります。
一方で、デメリットとしては、まず人脈を構築するための継続的な努力が必要であることが挙げられます。業界内で信頼を得るためには、実績を積み重ね、安定した成果を出し続けることが求められます。また、紹介元のネットワークに依存するため、案件の種類が限定され、多様な案件にアクセスしづらい点も考慮する必要があります。
さらに、トラブルが発生した際の対応も慎重に行う必要があります。紹介案件では、紹介元との関係を損なわないよう配慮しながら対応しなければならず、対応を誤ると紹介元の信用にも影響を与えてしまう可能性があります。そのため、仕事の質を維持し、信頼関係を長く続ける意識が欠かせません。
おすすめのフリーランスエージェント
フリーランスインフラエンジニアとして活動する際、信頼できるエージェントのサポートはなくてはならない存在です。ここでは、おすすめのフリーランスエージェントを3社ご紹介します。
ランサーズエージェント
ランサーズエージェントは、国内最大級のクラウドソーシングプラットフォーム「ランサーズ」が提供するフリーランスエージェントサービスです。ITエンジニア、クリエイター、デザイナーなど幅広い職種に対応しており、特にインフラエンジニア向けの案件にも力を入れています。
特徴として、まず豊富な高単価案件が挙げられます。案件の多くが月単価50万円〜100万円以上であり、クラウド移行、サーバー構築、大規模ネットワーク運用など、専門性の高い業務が中心です。インフラエンジニアとしてのスキルを活かし、高収入を目指したいフリーランスにとって魅力的な選択肢となるでしょう。
また、リモート案件が充実している点も強みの一つです。地方在住のフリーランスや、家庭の事情で通勤が難しいエンジニアにとって、柔軟な働き方が可能になります。特にクラウド関連やセキュリティ対策の分野では、リモート対応が可能な案件が増えており、場所を選ばずに働くことができます。
さらに、専任コンサルタントによるサポートも用意されており、フリーランス未経験者でも安心して利用できます。キャリア相談や案件の紹介を通じて、希望に合った仕事をスムーズに見つけることができます。
フリーランスとして独立を考えている方や、すでに独立していて条件の良い案件を探している方にとって、ランサーズエージェントは有力な選択肢の一つとなるでしょう。登録を検討することで、より良い案件に出会う機会を増やせます。
レバテックフリーランス
レバテックフリーランスは、ITエンジニアやクリエイター向けに案件を紹介する、業界最大級のフリーランスエージェントです。特に高単価の案件が豊富で、インフラエンジニアを含む幅広い職種に対応しています。
特徴として、まず高単価案件の充実度が挙げられます。月単価50万円以上の案件が多数あり、中には100万円を超える案件もあります。専門性の高いエンジニアにとって、安定した収入を確保しやすい環境が整っています。
また、専任のキャリアアドバイザーによるサポートも充実しており、案件の紹介だけでなく、キャリア形成に関する相談にも対応しています。フリーランスとしての働き方をさらに発展させたい方にとって、適切な案件を見つけやすい環境が整っています。
高単価案件や手厚いサポートを求めるエンジニアにとって、レバテックフリーランスは有力な選択肢の一つです。
フリーランスとしてキャリアアップを目指す方は、登録を検討すると良いでしょう。
Midworks
Midworksは、フリーランスエンジニア向けに手厚いサポートと福利厚生を提供するフリーランスエージェントです。正社員とフリーランスの「良いとこ取り」を目指し、自由度を保ちつつ、安定した働き方を実現する支援を行っています。
特徴として、まず正社員並みの福利厚生が挙げられます。フリーランスでありながら、仕事が途切れた際に最大で所得の60%を補償する制度(適用条件あり)や、確定申告のサポートを提供しており、安定した収入を維持しやすい環境が整っています。
また、高単価の案件が豊富で、月単価60万円〜80万円の案件が多く、スキル次第ではさらに高収入を狙うことも可能です。特にインフラエンジニア向けの案件では、クラウド環境の構築やセキュリティ対策など、専門性の高い業務が充実しています。
さらに、キャリアサポートも充実しており、専任のキャリアアドバイザーが案件の選定から交渉、契約手続きまでをサポートしてくれます。フリーランス未経験者でも安心して利用できるため、これから独立を考えている方にとって、特に適したエージェントと言えるでしょう。
まとめ
フリーランスのインフラエンジニアとして働くことは、スキルや経験を活かして収入アップや自由な働き方を実現する魅力的な選択肢です。特に、IT人材不足やクラウド技術の需要拡大に伴い、専門性の高いエンジニアが求められる時代が到来しています。AWSやAzureなどのスキルを持つエンジニアは、高単価案件を受注できる可能性が広がります。一方で、収入の不安定さや営業活動、税務処理などの課題も伴います。
本記事では、フリーランスエンジニアとして働くための準備として、実務経験の積み重ねやスキルの棚卸し、契約書の作成方法の学習が重要であることを解説しました。また、リスク管理や健康管理の重要性も強調しています。特に、収入の安定化を図るためには複数の案件を並行して受注し、リスクを分散させることが推奨されます。
資格については、AWS認定資格や情報処理技術者試験などが競争力を高める補強材料として有効ですが、実務経験が最も重要であることも指摘しました。案件獲得においては、フリーランスエージェントの活用や直接営業、人脈の構築がポイントとなります。
フリーランスインフラエンジニアの成功には、計画的な準備と継続的なスキルアップ、さらにはクライアントとの良好な関係構築が欠かせません。ぜひ、本記事を参考に、理想的な働き方を目指してみてください。